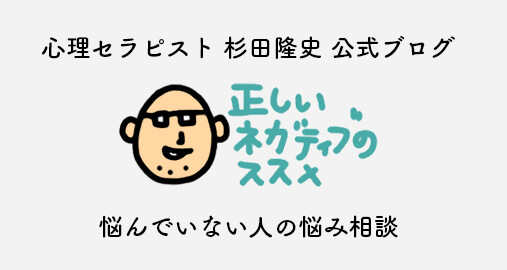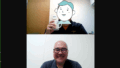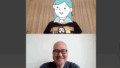先月アップした「クライアントさんインタビュー」を
読んだあなたも
まだ読んでいないあなたも
こんにちは。
妻とスーパーに買物に行く時、妻の見てぬ間に「つまみ系」をこっそりカゴに入れるのが上手くなり杉田です。
1週間お疲れさまでした!
えーと、先月このブログに、「クライアントさんインタビュー」として、
「いろんな自分があっていいよ: Tさんが「大人」になるまで」
という記事をアップしたんですけど、みなさん、ご覧になりましたか?
で、このインタビュー、本当はもっともっと解説を加えたかったんですけど、あまりにも記事が長くなると思って、ひかえたんですよね。
なので今回の記事で、改めて私が解説を加えたかったことをお話したいと思います。
あ、でもまずはそのインタビューを読んでないと、今回の記事の内容がわからないと思いますので、まだ読んでいない方は以下の記事をどうぞ!
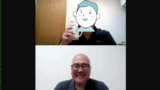
さ、ではさっそくいきますが、以下、解説を加えたかったことを箇条書きにしますね。
「過剰に子供」 と 「過剰に大人」
インタビューを受けてくださったTさん、このブログでもよく読まれている、
「成長が止まっている人」
という記事に当てはまる方だったんですね。
(まだ「成長が止まっている人」という記事を読んでいない方コチラからどうぞ)

で、この「成長が止まっている人」って記事、みなさんの中には、
「たしかに自分は「成長が止まっている人」に当てはまるんだけど、それだけじゃない何かがあるような・・・」
なんて思ってる方っていらっしゃいませんか?
以下の話は、そんな方のご参考になればと思うんですけど、この「成長が止まっている人」って、他の言い方をすると、
「子供時代、過剰に子供だったという悩み」
なんですよ。
親が過保護・過干渉・心配性だったりすると、子供は、「自分で考える・決める・行動する」という実感がなくて、それらをするのが苦手な大人になってしまうわけですね。
でもですね、ここからはちょっと話が複雑になるんですけど、
「成長が止まっている人」は、「子供時代、過剰に子供だったという悩み」なわけですが、
そういう人が同時に、
「子供時代、過剰に大人だったという悩み」
を抱えていることがあるんですよ。
要は、「過剰の子供」と「過剰に大人」という、正反対の悩みを同時に抱えている人がいるってことなんですね。
エッ、「ぜんぜん意味がわからない」ですって?
ですよね。ではここからはその解説をしますと、
まず「過剰に大人」とはなにかというと、いわゆる「良い子 」のことで、
子供時代、まわりの人(親・先生)の顔色をうかがって、自分を後回しにして、相手が喜びそうな行動ばかりとる人っているじゃないですか。(私もそうだった)
親の愚痴を聞くとか、
落ち込んでいる親を励ますとか、
仲の悪い家族の間に立ってフォローするとか、
おとなしくして、親に面倒をかけないようにするとか、
明るく振る舞って家族を雰囲気を和らげるとか。
そういうことするのって、「子供らしい子供じゃない」というか、
子供なのに大人のように気遣いをしたり、人の世話をしにいってますよね。だから、「子供時代、過剰に大人だった」。
で、「成長が止まっている人」に当てはまる人の中には、
①過剰に子供 ・・・ (小さな子供のように) できない、決められない、責任がとれない
②過剰に大人 ・・・ (大人の気遣いのように)自分を後回しにして他人を優先
という正反対の悩みを同時に抱えている人がいて、
むしろ、私のところに来られる「成長が止まっている人」は、
「①過剰に子供」を単独で抱えている人よりも、
「①過剰に子供」と「②過剰に大人 」の両方を抱えている人のほうが多いんですよ。
で、「①過剰に子供」を単独で抱えている人より、
「①過剰に子供」と「②過剰に大人 」の両方を抱えている人のほうが元気になるのが早い気がします。
やっぱり人間、「大人の部分がある」って元気になるにも大切なんでしょうね。
大人なのに「子供の部分しかない」ってキツイんだよなぁ。
で、インタビューにご協力いただいたTさんは、「②過剰に大人 」がまったくないわけではないかったけど、主に「①過剰に子供」を単独で抱えている方だったんですよね。
だから自信がつくまで特に大変だったわけです。
あ、ちなみに、私、個人セッション(心理セラピー)の中で、クライアントさんに、
「◯◯さんの悩みは、「過剰に子供であり、過剰に大人だった」という悩みなんですよ」
ってお伝えすると、
「そう言われると、すごくしっくりきます」
と言われる方って多いんですよ。
「成長が止まっている人」に当てはまるとは気づいていたけど、それだけではない、「過剰に大人」であるがゆえの悩みがあるのも感じてたんでしょうね。
あ、どうでしょう、「たしかに自分は「成長が止まっている人」に当てはまるんだけど、それだけじゃない何かがあるような・・・」みたいに思っていたあなた、
この話を聞いて、ちょっとスッキリする部分はありませんでしたか?
「アタマでわかる」から「カラダでわかる」へ
それからもう1つ「クライアントさんインタビュー」の中で、私が印象に残ったのは、以下の部分です。
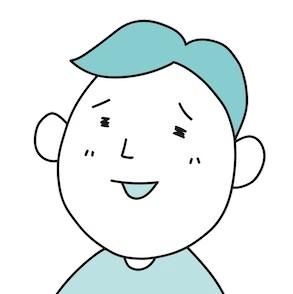
あと今日見てたんですけど、たぶん3回セラピー受けてて。
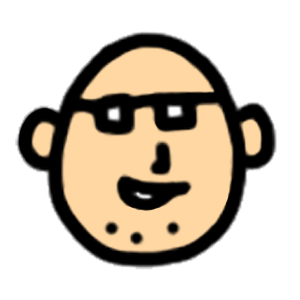
はい、受けられてますね
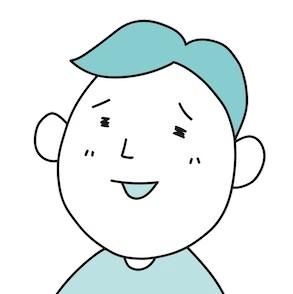
後半2回は、はっきり言って杉田さんも、もうお前は頑張る時期だっていうような感じだったから、初回みたいな聴き方ではなかったんだけど(笑)
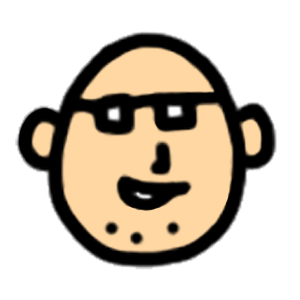
はい、はい(笑)
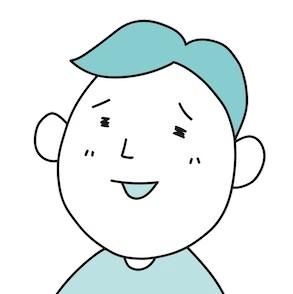
それを受けた後は、「何だよ!」って正直思ってたんですけど(笑)、ただ今になって思うと、やっぱそれもすごく必要な通過儀礼だったなって思いますね。頑張れって言ってたんだなって。それはセラピーでどうこうできる問題じゃないみたいな。
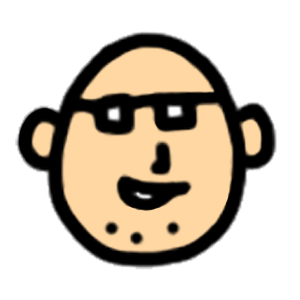
はい、はい
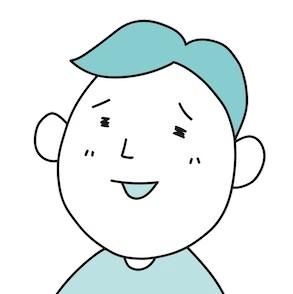
なんか、自分でやるしかないことってあるんですよね。やっぱりセラピストが何でもやってくれるわけじゃないし。
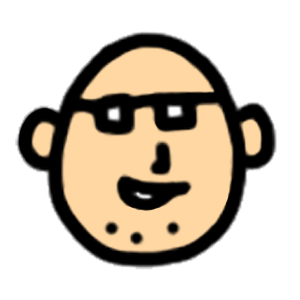
そうなんです。こちらはもうその人を信じて見守るしかない
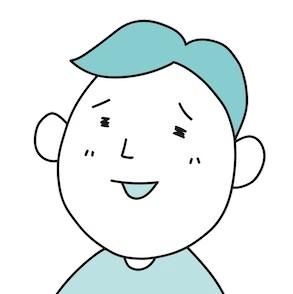
そう、当たり前だけど、杉田さんが僕と代わってやってくれるわけじゃないんで。
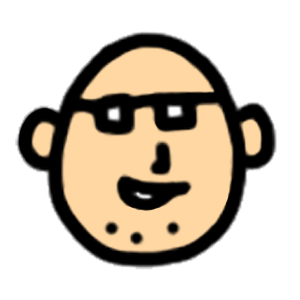
そう、「成長が止まっている人」って、だいたい「私をなんとかしてください」、「楽してうまくいく方法教えてください」って感じで来られますから(笑)
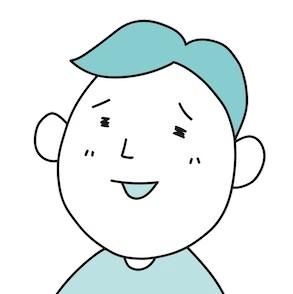
もう、まったくもってそうですよ(笑)
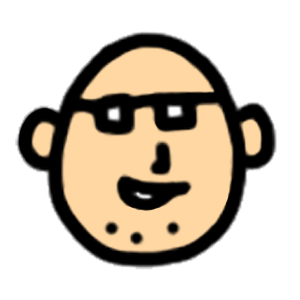
でもそれはできないんだっていうことを、体で理解していくってことが大切なんです
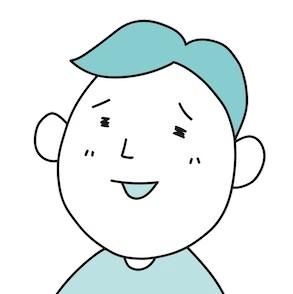
そうですね。
私、Tさんがこの話をされた時、「ちゃんと自分で気づいて、答えにたどり着いたんだなぁ」って、とても感慨深かったんですよ。
あ、この「成長が止まっている人」って特徴に1つに、「依存的」っていうのがあるんですけど、やはり個人セッション(心理セラピー)でも、
「私をなんとかしてください」
「楽してうまくいく方法教えてください」
みたいな感じで来られる方って多いんですね。
でもそういうスタンスだと、心理カウンセリング・セラピーでは変化が起きづらいんですよ。
だた、「私をなんとかしてください」、「楽してうまくいく方法教えてください」みたいに「人まかせ」になってしまうのは、
「その人にとっては当たり前過ぎて、自分がそう思っていることすら意識できないくらいデフォルト」なので、
そのスタンスはマズイと言われても困るわけですよね。それ以外のスタンスを知らないわけですから。
なので、私、そういう方に、
「なんとか能動的にセラピーを受けるってことを伝えられないかな?」
って長い間思ってたんですけど、ようやく「こう伝えればいいのか!」ってフレーズを閃いて、それをアップしたのが、実はちょっと前のこの記事だったんです。

あ、なんか話がちょっと飛んでしまいましたが、何度かこのブログの中でお話していることですが、
バランスのとれた大人になるには、
- 自分でできることは、自分でする(自立)
- 自分でできないことは、人に助けを求められる(依存)
その両方をできる必要があるんですね。
なので、「依存」ってこと自体が悪いとか・ダメだとかではないんですよ。むしろ、依存が必要が時は、依存ができないといけない。
ただ、「成長が止まっている人」は、「自立」と「依存」のバランスがバグっているわけで、
「本来、自分にしかできない領域を、他人がやってくれるものだ」
って思ってるんですよね。
でも、そう思ってしまうこと自体が悪いわけではないですけど、社会や対人関係の中で要求される自立のレベルに達してないから、生活するうえで、問題が起きやすいんですよ。
なので、本人は、「依存的なのを、なんとかしなきゃいけない」ってことはアタマではわかっているけど、
結局、いつも「でもどうしたらいいかわからない。誰かなんとかして!」ってなってしまうんですよね。
でもTさんは、ある段階で、「いや、これは、人になんとかしてもらう領域ではなく、自分でなんとかしなきゃいけないことなんだ」ってことを真に気づかれたんでしょうね。
「自分でやるしかない」ってことが、「アタマでわかる」から「カラダでわかる」になった。
こういうのが、過去記事でもお話した、
「心の悩み」は、人から「答え」を教えてもらってもピンとこない。
自分で「答え」に到達する必要がある。
ってことなんですよ。
なので、私、Tさんから「成長が止まっている人」の核心である気づき(自立)に至るプロセスをお聴きできて、とても感慨深かったんですよね。
あ、いけない、気がづけばすっかり長い記事になってしまいました。
やっぱり【インタビュー後記】にこの解説を入れなくてよかった(笑)。
さ、ということで、今回は、先日アップした「クライアントさんインタビュー」、
「いろんな自分があっていいよ: Tさんが「大人」になるまで」
という記事への追加の解説でしたとさ。
それでは今回はココまでにします。
ここまで読んでくださって、ありがとうございました。
また次回お会いしましょう!