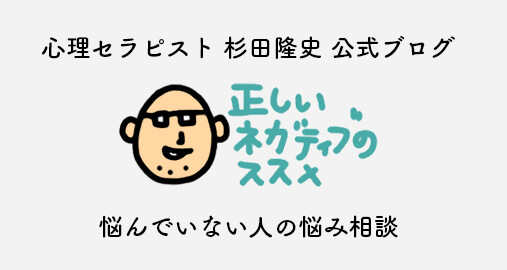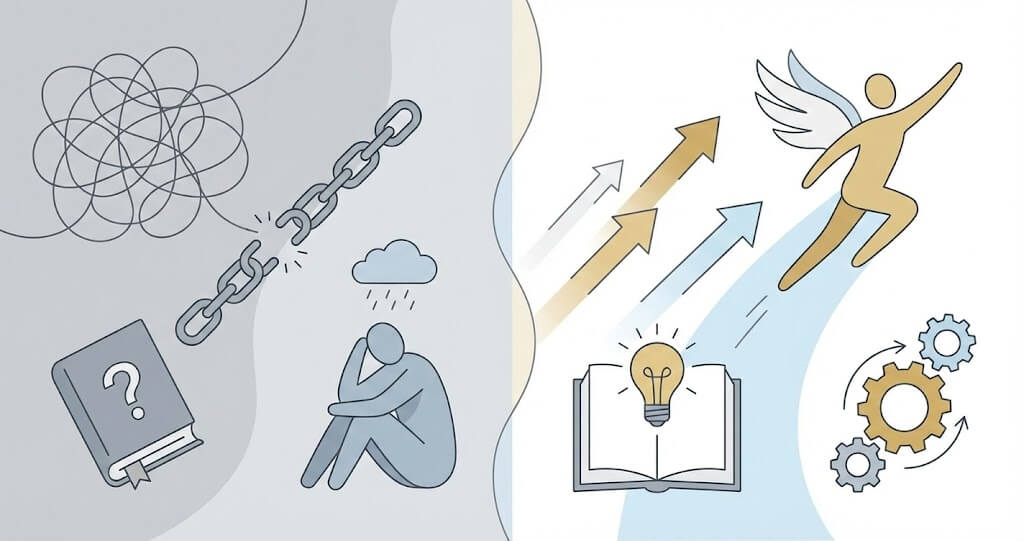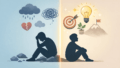心理カウンセリング・セラピーを受けたことが、
あるあなたも
ないあなたも
こんにちは。
マックのエッグチーズバーガーに卵の殻がガッツリ入っていて思わぬカルシウム補給になり杉田です。
1週間お疲れさまでした!
えーと、私、かれこれ18年以上、心理セラピストとして活動してきたので、たくさんの方にお会いしてきたんですけど、
私が同じようにセラピーをやったとしても、「クライアントさんの変化の速度」って、ホント人それぞれなんですよね。
なので、今回は、私の経験の中で感じた、
変化が早い人
変化が遅い人
の特徴をそれぞれお話をさせていただこうかなと思います。
あ、でもこんな話をすると、
「私、変化が遅い人に当てはまりそう!」
なんてイヤな予感がする方もいらっしゃるかもしれませんが(笑)、
どうかご安心ください。
まず私自身が、「変化が早い人」に当てはまらないですから(笑)。
でもちゃんと変化しましたからね。
ただ、心理カウンセリング・セラピーとかって、他の人がどんな感じに受けてるかわからないじゃないですか。
なので、今回の記事が、「悩みの解決が早い人ってこういう感じなのか」っていう参考になればと思っています。
さ、それでは、以下、「変化が早い人」と「変化が遅い人」の順番で特徴を箇条書きにしますね。
変化が早い人の特徴
気づきの能力が高い
あ、ちょっと前に、「答えがピンとくる悩み、こない悩み」という記事をアップしたんですけど、みなさん、ご覧になりましたか?
(まだ読んでいらっしゃらない方はコチラからどうぞ)
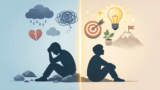
この記事、「なぜ心理カウンセリング・セラピーでは、「答え」を言わないのか?」という話をしたんですけど、結論としては、
「心の悩み」は、人から「答え」を教えてもらってもピンとこないことが多いので、自分で「答え」にたどりつくする必要があるんですよ。
だから心理カウンセラー・セラピストは、「答え」を言ったりしないんですよ。
なんて話をしたんですね。
で、そのことからわかるように、心理カウンセリング・セラピーを受けて「変化が早い人」って、
「自分で「答え」にたどり着くのが早い人」
ってことになるわけですけど、そのために必要なのは、
「気づき」
なんです。
あ、この「気づき」って、
- 自分が思いもよらなかったことに気づく
- うっすら気づいていたけど、見ないようにしていたことに気づく
- すでに気づいていたけど、認めたくなかったことを認めないといけないことに気づく
みたいに、自分の死角になっていたところに気づくと、なにかが腑に落ちて変化が起きるんですよ。
でもこの「気づきの能力」って、けっこう個人差があるんです。
たとえば、変化が早いクライアントさんって、もうセラピー中に、
「あ、私のほうがよっぽど相手に期待してる。恥ずかしい・・・」
「あ、お母さんから見れば、私は何を考えているかわからないですよね・・・私が言えば良かったのかな?」
「ん? 私、ものすごく確率の低いこと望んでますよね。そうか無理なのか・・・」
みたいに、お話しながら次々に気づきがあったりするんですよ。
そういう方の変化はホント早いです。
(ほとんどのクラアントさんは、セラピー後にジワジワと気づきがある)
で、そういうセラピー中に次々に気づきがある方を拝見すると、
ってことをホント実感するんですよ。
行動力がある
「行動力がある人」というのは、いろいろな分野でその強みを発揮しますよね。
心理カウンセリング・セラピーでもやっぱりそうで、先ほどお話した、「気づきの能力が高い」にプラスして、
「行動力がある」
という人は、最も変化の早い人ではないかと思います。
ちなみに私の行動力は、「ふつう」くらいでしょうか。自分が腑に落ちないことは、あまり動けないんですけど、腑に落ちることはガンガン動けるんですが。
でも本当に行動力がある人って、どんな時でも動けるんだよなぁ。
変化が遅い人の特徴
答えを教えてもらおうとする質問が多い
この「答えを教えてもらおうとする質問」って、
「どうしたら◯◯になれますか?」
「◯◯でいいんですよね?」
「私、どうしたらいいですか?」
みたいな質問のことです。
セラピー中にそういう質問が多い人は、ほぼ変化が遅いです。
というのは、先ほどお話したように、「心の悩み」って、人に「答え」を聞いてもピンとこないんですよね。
「自分で」気づいて、「答え」にたどりつく必要がある。
なので、人に「答え」を教えてもらおうとする質問って、一番意味がない質問になっちゃうんですよ。
あ、ちなみに、心理カウンセリング・セラピーで、クライアントさんに話していただく目的って、カウンセラー・セラピストに「情報提供するため」というより、
「クライアントさん自身が気づくために話す」
「クライアントさんが自分で答えにたどり着くために話す」
ってことなんですよね。
おとなしくしていれば、人になんとかしてもらえると思っている
「体の不調」でお医者さんに行く時って、「おとなしくして、お医者さんの言うことを聞いていればなんとかしてもらえる」じゃないですか。
だから、「心の不調」で悩んでいる時も、お医者さんに行くような感じでいいのかなと思うかもしれませんが、
心理カンセリング・セラピーって、それとは違って、お医者さんがやっているような「治療」ではないんですよね。
つまり、心理カウンセラー・セラピストが、あなたを変えてくれるわけではないんです。
だから、「おとなしくしていれば、人になんとかしてもらえる」っていう感じとは違って、「自分でなんとかする」っていうマインドが必要なんですよ。
あ、でもそんなこと言いつつ、じゃあ、私が昔、心理セラピーを受けていた時って、
私自身に「自分でなんとかする」っていうマインドがあったかというと、わからないんですよね。そんなこと意識しなかった。
ただ、私、「おとなしくしていれば心理カウンセラー・セラピストがなんとかしてくれる」とは微塵も思ってなかったんですよ。
なので、私は、「自分でなんとかする」っていうマインドは、自分では当たり前過ぎて意識できないくらいデフォルトだったのかなと思うんです。
となると、「おとなしくしていれば、人になんとかしてもらえる」って思っている人も、
本人は当たり前過ぎて意識できないくらい、それがデフォルトなのかもしれないんですよね。
「変化する」とはどういうことか?
さ、ということで、ここまで、「変化が早い人」と「変化が遅い人」の特徴をお話してきましたけど、その違いは、
変化が早い人・・・能動的
変化が遅い人・・・受動的
って言うのが一番わかりやすいかなって思います。
ではなぜ「能動的」なほうが、変化が早くなるのかという話をここからしたいと思うんですけど、
まず、心理カウンセリング・セラピーに来るクライアントさんって、
「変わりたい」
「変わりたくない」
という両方の気持ちを同時に持った状態でいらっしゃるんですよね。
で、クライアントさん、今現在「変わりたいけど、変われていない」ってことは、
「変わりたい < 変わりたくない」
ってなってるってことなんです。
でも人が変わる時って、それが
「変わりたい > 変わりたくない」
ってならないといけないわけですよ。
もっと具体的に言うなら、クライアントさんが、
「今のままでいるほうがツラい。怖いけど変わる」
ってなった時に、人はジワジワと変わっていくんですよね。たいていは自分がそう決断した瞬間は自覚できないんですが。
(そのへんの詳しい話はコチラからどうぞ)

で、「変わりたい」を「 変わりたくない」より強くするのって、誰かがあなたをそう変えてくれるわけではなくて、あなた自身がそうしないといけないんですよ。
だから、「誰かに変えてもらえる」と思っている人は、いつまでたっても・・・ってなるわけです。
あ、ちなみに、ちゃんと心得ている心理カウンセラー・セラピストって、
「自分がこのクライントさんを変えてやろう」
とは思ってないんですよ。変わるも変わらないも、クライアントさんの自由。
逆に、「自分がこのクライントさんを変えてやろう」と思っているカウンセラー・セラピストって、カウンセリング・セラピーがうまくいかなくなるんです。
というのは、それって、「この子は自分でできない」と思って、なんでも先回りしてやってしまう親と同じで、
親がそういう態度で接していると、子供は、「自分がダメだから、親がやるんだ。自分は信頼されてないんだ」って受け取りやすいんですよね。
つまり、親が子供の力を信じてないと、子供は力を発揮できなくなる。
それと同じで、「自分がこのクライントさんを変えてやろう」って思っているカウンセラー・セラピストって、
「クライアントさん自身の力で解決できない」って思っているわけですよ。だからカウンセラー・セラピスト自身がなんとかしようと思っちゃう。
そういうスタンスって意外と伝わっちゃって、クライアントさんが力を発揮できなくなるんですよね。
受動的なクライアントさんはどうすればいいのか?
自分が気づいていないことを気づこうとして話す
さ、ということで、以上のことから、
心理カウンセリング・セラピーを受ける時は、「受動的」よりも「能動的」のほうが良さそうですよ
ってことなんですけど、
みなさんの中には、「ゲッ、私は受動的な方に当てはまってしまう!」なんて思っている方もいらっしゃるかもしれません。
でも先ほどもふれましたけど、受動的なクライアントさんって、もう受動的が当たり前すぎで、どうすれば能動的になれるかわからなかったりするんですよね。
なので、ここからは、
「受動的なクライアントさんはどうすればいいのか?」
ってお話をしたいと思うんですけど、
私、ホームページやブログに、
「個人セッション(心理セラピー)で、受動的・依存的なクライアントさんは変わらないですよ」
みたいなことをちょこちょこ書いているので、
それに当てはまるクライアントさんでも、けっこう張り切って個人セッションにいらっしゃることが多いんですよ。
でもそういう方たちの張り切り方って、
心理カウンセラー・セラピストに「自分のことを細かく話す」ことが能動的だと思ってるんですね。で、細かく情報提供すれば、あとなんとかしてもらえると思っている。
でも先ほどお話したように、心理カウンセリング・セラピーで、クライアントさんに話していただく目的って、
「クライアントさん自身が気づくために話す」
「クライアントさんが自分で答えにたどり着くために話す」
ものなので、カウンセラー・セラピストに一生懸命「自分のことを細かく話して」情報提供することより、
「クライアントさん自身が、自分が気づいていないことを気づこうとして話しているか?」
ってことのほうが、はるかに重要なんですよ。そっちを張り切っていただけたらと。
そうしようとすることが、「能動的に心理カウンセリング・セラピーを受ける」ってことでしょうか。
「自分」という会社の社長になったつもりで受ける
それからもう1つ、受動的なクライアントさんがどうすれいいかを例え話としてお伝えすると,
まずあなた自身を、「会社」だと思ってみてくださいね。
能動的な人は、自分のことを「社長」だと思っていて、
受動的な人は、自分のことを、「ヒラ社員」だと思っている、
例えていうなら、それくらいの違いがあると思います。
で、自分が社長だと思っていると、会社に問題が起こると、すごく「自分ごと」として捉えるじゃないですか。自分が責任を持って先頭に立たないといけない。
でも自分がヒラ社員だと思っていると、会社に問題が起こっても、たしかに自分が勤務している会社だから「自分ごと」なんだけど、その気持ちは薄いというか、
どこか「上の誰かがやってくれるんじゃないか」みたいに思ってしまう。
同じ「自分ごと」として捉えていても、能動的な人と受動的な人って、それくらい意識の違いがある気がするんですよね。
なので、心理カウンセリング・セラピーを受ける時って、
カウンセリング・セラピーを「自分」という会社の社長になったつもりで受ける
というのがいいのかもしれません。
具体的には、あなたは社の代表としてただ一人カウンセリング・セラピーを受けに来ていていて、
そこでの内容は他の社員は誰も知らなくて、あなたがカウンセリング・セラピーを受けてどうだったか知りたくて、他の社員は首を長くして待っている。
会社に帰ってからあなたが先頭に立って社員にその内容を説明して、
トップとして率先して今後どうするか考え、あなたの責任で実行しないといけない。
そんな状況だとすると、あなたはどういう態度でカウンセリング・セラピーを受けますか?
ってことなんですよね。
いやぁ、気がつけば、だいぶ長い記事になってしまいましたけど、
実は今回の記事、私、ずっと書きたかった内容なんですけど、何度トライしたても、うまくまとめられなくて、長い間アップできなかったんですよね。
なので、ようやく書き上げることができて、ホッとしましたよ。
「心理カウンセリング・セラピーを受ける時、どうも受動的・依存的になっちゃう」という方に少しでも参考になれば幸いです。
それでは今回はココまでにします。
ここまで読んでくださって、ありがとうございました。
また次回お会いしましょう!